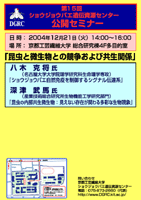第15回 公開セミナー | |
|
日時:2004年12月21日(火)14時00分〜16時00分 | |
|
八木 克将 氏 演題:『ショウジョウバエ自然免疫を制御するシグナル伝達系』 要旨: 生物は体内に侵入してくる微生物やウィルスなどを排除する生体防御機構を発達させている。自然免疫は多くの多細胞生物に見られる生体防御機構で、脊椎動物や昆虫も含む多くの生物が持つ生体防御機構である。これまでにショウジョウバエでは自然免疫のうち、微生物の感染に反応し、抗菌ペプチドの産生を行う系が特に詳しく解析されてきた。その過程で自然免疫のシグナル伝達機構に昆虫とほ乳類の間で数多くの共通性があることが明らかになってきた。 | |
|
深津 武馬 氏 要旨:
昆虫類は既知の生物多様性の過半数をしめており、陸上生態系の中核をなす生物群である。その半数以上は何らかの微生物と恒常的もしくは半恒常的な共生関係をむすんでいるものと推定されている。 |
ショウジョウバエ遺伝資源センターでこれまでに開催された他のセミナーはこちら